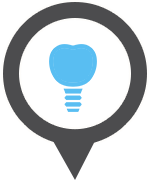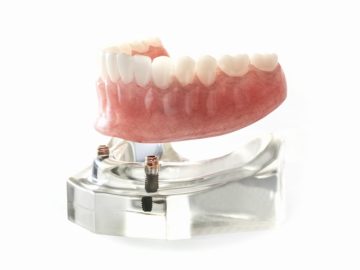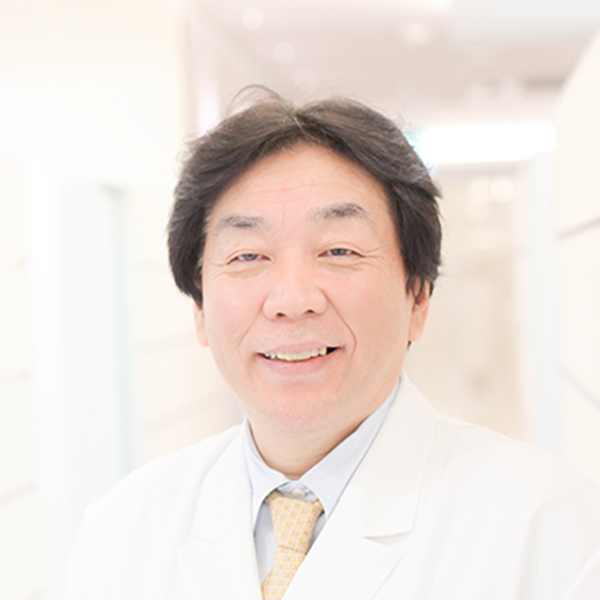
- この記事の監修者
- 医療法人社団「朋優会」理事長。歯科医師・インプラント専門医。国際インプラント学士会(I.C.O.I.)メンバー。米国インプラント学会(A.O.)アクティブメンバー。欧州インプラント学会(E.A.O.)メンバー。O.S.I.アドバンスドトレーニングコース 講師。
https://e-implant-tokyo.com/smile-implant/

整骨院で施術を受けた後、症状が改善しないまま終わった経験はありませんか?
最近は、肩こりや腰痛の原因が噛み合わせの不調からくるのがわかっています。
噛み合わせの不調は、口だけでなく全身の健康状態に影響があるほどです。
とはいえ、噛み合わせの悪さがどう全身に影響を及ぼすのかよくわからない方も多いと思います。
そこで今回は、噛み合わせの悪さで起きやすいトラブルや治療法といったことについて解説していきます。
目次
- 1 歯を失うと噛み合わせが悪くなる
- 2 噛み合わせの不調で起きやすいトラブル
- 3 全身に起きるトラブル
- 3−1:肩こり・腰痛
- 3−2:発音障害
- 3−3:顎関節症
- 3−4:消化不良
- 3−5:虫歯・歯周病
- 4 精神的に起きるトラブル
- 4−1:イライラしやすい
- 5 噛み合わせを改善する「3つの治療法」
- 5−1:入れ歯
- 5−2:ブリッジ
- 5−3:インプラント
- 6 歯を補充して終わりは危険
- 7 噛み合わせを整えて快適に過ごそう
1 歯を失うと噛み合わせが悪くなる

口は上下合わせて28本の歯で、噛み合わせのバランスを取っています。
また、噛み合わせは歯だけでなく、口周りの筋肉や骨などで全身のバランスを保っています。そんな多くの組織で成り立っている噛み合わせは、1本の歯を失うとバランスが崩れてしまうケースがほとんどです。
一般的には、それぞれの歯にかかる力は決まっていて、負担がかかりすぎないようになっています。
しかし、歯を1本失った場合、他の歯に負担がかかるようになり、歯の寿命が短くなる可能性が高いです。歯を失った状態が長いほど、口の中は少しずつ崩壊していきます。
例えば、失った歯の両隣の歯が傾いたり、伸びたりしてどんどん噛み合わせがズレていきます。そうなると、見た目が悪くなるだけでなく、しっかりと噛めなくなって、いろんなトラブルが起きるようになります。
2 噛み合わせの不調で起きやすいトラブル

噛み合わせが悪い場合には、大きく分けて次の2つのトラブルが起きやすいです。
・全身に起こるトラブル
・精神的に起こるトラブル
それぞれについて、次から詳しく解説していきます。
3 全身に起きるトラブル

3−1:肩こり・腰痛

肩こりや腰痛は、悪い姿勢や運動不足以外に、噛み合わせの不調が原因なケースがあります。
例えば、頭が右に傾くとバランスを取ろうと左肩に力がかかって、次に左肩が辛くなると右の腰に力がかかるようになります。
このように一部のバランスが崩れると、それをカバーするように他の部分に負担がかかるといったパターンを繰り返して、痛みが出る箇所がどんどん増えていく傾向があります。
頭が傾くのは、下あごと頭蓋骨が繋がっているからです。
つまり頭蓋骨と下あごは、咀嚼筋や側頭筋などの筋肉と繋がっていて、上下の噛み合わせが合わなくなると、筋肉への力のかかり方が均等ではなくなり、頭部が傾くようになります。
頭部が傾いた分のバランスを全身でとろうとして、体中の筋肉が緊張状態になり、肩や腰といった部分に痛みが生じるようになるのです。
3−2:発音障害

噛み合わせの悪さは、発音にも影響が出やすいです。
例えば、歯を1本失った場合は、話す時に隙間から空気が漏れてハッキリとした発音がしづらくなります。
特に「サ」行や「ハ」行などは発音しづらく、こもった話し方になりやすいです。
3−3:顎関節症

顎関節症とは、下あごを動かすときに使う関節や筋肉に炎症が起きる病気のことです。
下あごは耳の横の関節にぶら下がっていて、頭を支えている状態になっています。
大人の頭は約6キロの重さがあり、下あごは頭の重さを支えながら食事をしたり、食いしばったりと負荷がかかりやすい状態です。
そんな状態で噛み合わせが悪くなると、関節や筋肉に負担がかかって痛みが生じたり、口が大きく開けられなかったりする症状が出るようになります。
3−4:消化不良

噛み合わせが悪いと食べ物を噛み砕いたり、すり潰したりがうまく機能せずに、食べ物が細かくなっていない状態で飲み込む癖がつきやすいです。
そうなると、消化器官に負担がかかって、消化不良を起こすケースも少なくありません。
また、噛み合わせがズレていると全身のズレにも繋がり、骨格が歪むようになります。
骨格が歪むと骨が内臓を圧迫して、正常に機能しなくなる可能性があります。
3−5:虫歯・歯周病

歯を失った場合、噛み合わせのバランスが崩れて噛める部分や噛めない部分がでてくるようになります。
噛めるところでは、食べ物を細かく噛み砕けるので、ある程度歯の表面に汚れが残っても唾液で流されやすいです。
しかし噛めないところでは、食べ物が大きいまま残って、唾液でも流れにくくなります。その結果、虫歯や歯周病といった病気になりやすいです。
また、咬合性外傷といって、噛み合わせによって骨が溶けてしまう症状が出ます。
噛み合わせのバランスが悪い場合には、一部分の歯にだけ過度な負担がかかりがちです。
骨は過度な刺激が加わると溶けてなくなり、最悪の場合には、歯がグラグラと動いて抜けてしまうこともあるほどです。
4 精神的に起きるトラブル

噛み合わせの不調が原因で、精神的に起きるトラブルは次の通りです。
4−1:イライラしやすい

最近の研究では、噛み合わせの不調が脳にも影響すると報告されています。
頭蓋骨と下あごは繋がっていて、下あごがズレると頭の位置も傾いてしまいます。
そのときに神経や血管を圧迫して、十分な酸素や栄養が送られず、脳の働きが鈍くなる可能性が高いです。
脳の働きが鈍くなると、イライラしたり、怒りっぽくなったりする傾向があります。
また、神経や血管を圧迫して、必要な量の血液が送られなくなると酷い場合には、頭がボーッとしてうつ状態になるケースもあるほどです。
5 噛み合わせを改善する「3つの治療法」

歯を失った状態から噛み合わせを良くするには、次の3つの治療法があります。
・入れ歯
・ブリッジ
・インプラント
それぞれの治療法について、詳しく見ていきましょう。
5−1:入れ歯

入れ歯は、失った部分にはめて使うようになります。
入れ歯を入れることで噛めるようにはなりますが、入れ歯に使用する素材によってはしっかりと噛めずに噛み合わせが改善しない場合もあります。
特に保険の入れ歯は、プラスチックの材質でできていて、固い物や引きちぎる動作が必要な食べ物には対応できないことが多いです。
また、プラスチックでは精密な噛み合わせを再現するのが難しくズレが生じやすいです。
そのため、保険の入れ歯を使用する場合には、頭痛や肩こりなどの症状が改善しないことがあります。
5−2:ブリッジ

ブリッジは、失った歯の両側の歯を削って、その上から繋がった被せ物を装着する方法です。
3本分の歯を2本の歯で支えるため、両側の歯に負担がかかりますが、しっかりと噛めるようになります。
ブリッジは、入れ歯に比べて噛み合わせが安定しやすいです。
しかし、虫歯になっていない自身の歯を削るのがデメリットになります。
5−3:インプラント

インプラントは、失った歯の部分にインプラントを入れて見た目や噛む機能を回復させる治療法です。
インプラントは、保険外の治療になりますが、他の歯に負担をかけずに理想的な見た目や噛み合わせを実現できます。
インプラントに取り付ける被せ物は、セラミックやジルコニアなど優れた材質を使用するケースが多く、噛む力にも耐えて精密な噛み合わせの作製が可能です。
失った歯と同じような見た目や噛む機能を再現でき、噛み合わせからくる症状を改善できる可能性が高いです。
6 歯を補充して終わりは危険

入れ歯、ブリッジやインプラントのどれかの治療を行っても、全体の噛み合わせのバランスが悪いままでは症状が改善しにくいです。
補充したら終わりではなく、噛み合わせの調整をしっかりと行ってくれる歯科医院で治療をするのが大事です。
補充した歯は、毎日使う物なので、徐々に噛み合わせがすり減っていきます。
噛み合わせがすり減ったままにしておくと、歯や関節などに負担がかかって、全身にもトラブルが起きやすいです。
そのため、定期的に噛み合わせの調整や噛み合わせのチェックをしてもらいましょう。
7 噛み合わせを整えて快適に過ごそう

噛み合わせの不調は、口だけの問題だけでなく全身の健康にも関わってきます。
歯を1本失っただけでも噛み合わせのバランスが崩れて、いろんな部分に影響が出てきます。
そのため歯を失った時には、そのままにせず早めに歯科医院で治療を受けましょう。
しかし歯科医院によっては、噛み合わせを重要視していない医院も存在します。
そうなると、歯を補充したのに体調が悪かったり、他の歯に痛みが出たりといったトラブルが起きやすいです。
治療をするときは、失った部分だけでなく、全体の噛み合わせを見て調整してくれる歯科医院を選ぶのが大切です。
体調が悪く、肩こりや頭痛といった症状がいつまでも続くような方は、一度、歯科院で噛み合わせを診てもらうのがおすすめです。