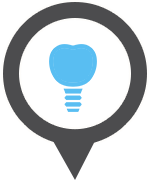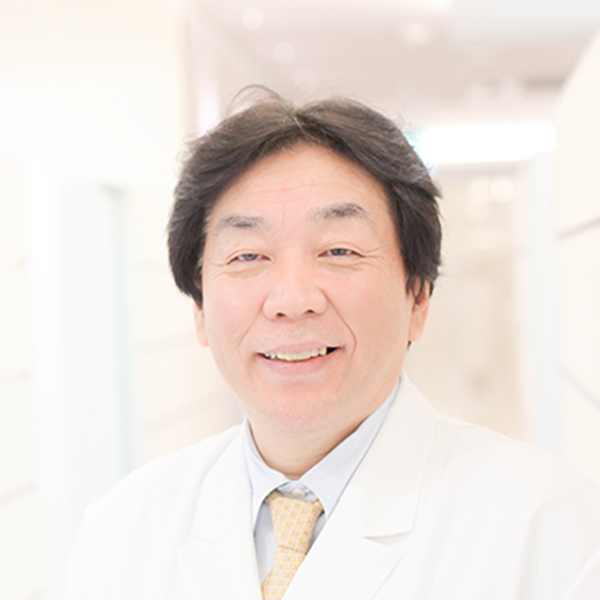
- この記事の監修者
- 医療法人社団「朋優会」理事長。歯科医師・インプラント専門医。国際インプラント学士会(I.C.O.I.)メンバー。米国インプラント学会(A.O.)アクティブメンバー。欧州インプラント学会(E.A.O.)メンバー。O.S.I.アドバンスドトレーニングコース 講師。
https://e-implant-tokyo.com/smile-implant/

結論から言うと、「骨粗しょう症の方でもインプラントはできます。
しかし、骨粗しょう症の方が、インプラント治療をするのには条件があります。
その条件をクリアできた場合には、インプラントをすることが可能です。
骨粗しょう症が原因で、インプラント治療を断られた方も、他の歯科医院でインプラントができる可能性があります。「インプラントをしたいけど、骨粗しょう症だから・・・」とお悩みの方は、今回の記事を是非、参考にして下さい。
目次
- 1 インプラントができないのは骨粗しょう症が原因?
- 1-1:副作用が起こる原因
- 2 「顎骨壊死」は必ず起きる症状ではない
- 3 インプラントができる可能性が高くなる「5つの条件」
- 3-1:使っている薬がBP製剤ではない
- 3-2:薬の服用を止めることができる
- 3-3:服用する薬の量が多くない
- 3-4:口の中を清潔に保つことができる
- 3-5:インプラント手術をする術者の知識や技術がある
- 4 骨粗しょう症でもインプラントを諦めない
1 インプラントができないのは骨粗しょう症が原因?

「骨粗しょう症=インプラントができない」と思っている方も多いのではないでしょうか?
確かに骨粗しょう症は、骨の中がスカスカになってしまい、骨の強度が弱くなって骨折しやすくなる病気です。
インプラントは、顎の骨の中に埋める外科手術が必要になるため、骨粗しょう症では、インプラントができないように思いがちです。
しかし、インプラントができないと判断される多くの原因は、病気ではなく薬です。
骨粗しょう症の方のほとんどが、ビスフォスフォネート製剤といって骨を破壊する細胞を抑える効果がある薬を服用しています。
この、ビスフォスフォネート製剤が、インプラントができるか大きく関わってきます。
ビスフォスフォネート製剤は、骨粗しょう症に効果的で、一般的にも処方される薬です。
しかし、どんな薬にも副作用があります。ビスフォスフォネート製剤の副作用は、顎骨壊死です。
顎骨壊死とは、その名の通り、顎の骨が腐ることです。
ビスフォスフォネート製剤を服用している時に、正しい処置をしないまま抜歯や外科手術(インプラント含む)をすると、顎骨壊死になったり、炎症が悪化したりする可能性があります。
1-1:副作用が起こる原因

骨は、再生と破壊を繰り返しています。
骨が破壊する時に、カルシウムも一緒に破壊されます。
病気ではない人の場合では、カルシウムが破壊されても再生する時に、カルシウムが骨の中に取り込まれるので何の問題もありません。
しかし、骨粗しょう症の方の場合は、再生の働きが鈍くなっている状態です。
そのため、破壊の時にカルシウムが一緒に破壊されると、骨がどんどん弱くなっていくのです。
骨がこれ以上弱くなると骨折しやすくなるので、破壊の働きをさせないようにするビスフォスフォネート製剤を使って、骨の破壊を制御していきます。
ビスフォスフォネート製剤は、骨を破壊するのを防げる一方で、骨を作り出すことや軟組織を作り出す機能も抑えてしまいます。
再生する機能が働かない時に、間違った外科手術をすると、傷口から細菌が侵入して炎症を引き起こしたり、酷い場合には、顎骨壊死になったりする可能性があるのです。
2 「顎骨壊死」は必ず起きる症状ではない

ビスフォスフォネート製剤を服用していると、必ずしも顎骨壊死になるわけではありません。
実際に、ビスフォスフォネート製剤を錠剤で服用していて、顎骨壊死になる確率は約0.01%程度と言われています。
また、症状が起こる場合は、服用から3年以上経過してから発症することが多いと報告されています。
3 インプラントができる可能性が高くなる「5つの条件」

とはいえ、骨粗しょう症という病気やビスフォスフォネート剤の副作用から、インプラント治療を断る歯科医院もあります。
そこで、骨粗しょう症でもインプラントができる可能性が高くなる「5つの条件」について、詳しく解説していきます。
3-1:服用している薬がビスフォスフォネート剤ではない

骨粗しょう症の薬には、いくつか種類があって、症状や進行状況によって使う薬が変わります。顎骨壊死を引き起こす副作用を持つ薬は、今のところビスフォスフォネートだけだと言われています。
その他のホルモン剤などの薬を、骨粗しょう症予防で服用している場合は、問題なくインプラントができることが、ほとんどです。
3-2:薬の服用を止めることができる

薬の服用を止めることができればインプラン治療はできます。
一時的に、薬の服用を止めることで、細胞に新しい骨や軟組織を作り出す働きを再開してもらい、顎骨壊死を防ぐことが目的になります。
薬を止める期間は、人によって異なりますが、インプラント手術をする3ヶ月前からが一般的です。また、口の状態や傷の治り方では、インプラント手術後の3ヶ月も薬を止めることもあります。
3-3:薬の服用量が多くない

摂取する薬の服用量が多い時には、薬を止めることが難しい場合があります。
特に錠剤ではなく、定期的に注射で薬を取り入れている方は、錠剤の服用よりも摂取する濃度が高いため、副作用を起こすリスクも高くなりやすいです。
内科の担当医に相談して、薬の中断が厳しい場合には、インプラントをするのが難しくなります。
3-4:口の中を清潔に保つことができる

ビスフォスフォネート製剤を使用していても、服用量が少なかったり、一時的に止めることができたりする場合には、インプラントができる可能性は高くなります。
インプラント治療が可能なときには、口の中を清潔に保つことが重要です。
口の中の細菌が多いと、感染するリスクが上がります。
特に、虫歯や歯周病といった症状がある状態でインプラントをすることは、危険です。
免疫力が低下している時には、さらに感染するリスクが上がるため、顎骨壊死や炎症を引き起こす確率が高くなるので、虫歯治療や歯周病治療を終わらせて、細菌の数を減らしてからインプラント治療を始めるのが重要です。
インプラント治療が終わった後も、日々の歯磨きはもちろん、定期的な検診で、歯垢や歯石を除去して歯の予防を続けるようにしましょう。
3-5:インプラント手術をする術者に知識や技術がある

骨粗しょう症といった病気では、患者さん側の対処も必要ですが、歯科医院側の対処力も必要です。特に、インプラント手術をする歯科医師の知識や技術は欠かせません。
例えば、内科医と相談して、薬の服用を止めることが可能だが、傷口を露出させないようにしてほしいと言われたとします。骨や傷口を露出させてしまうと、感染しやすくなり顎骨壊死になる可能性が高くなるためです。傷口を完全に覆うような、技術の腕が歯科医師に備わっているかが、見極めどころです。
しかし、知識や技術がある歯科医師を見極めるのは、簡単ではありません。
歯科医院のHP(ホームページ)があるのなら、歯科医師が、今までどんなインプラント手術をしてきたか、学会や勉強会に定期的に参加していて、学んでいる姿勢などを確認して見ましょう。
4 骨粗しょう症でもインプラントを諦めない

骨粗しょう症でもインプラントをするのは可能です。
特に、現在は歯科医療も進み、インプラント治療をする前にCT撮影をして骨の状態を分析することができます。これを行うことで、骨の密度や骨の量を確認でき、インプラントができるかどうかの判断を行えます。
骨粗しょう症が原因で諦めるのではなく、まずは、歯科医院に骨粗しょう症であること、薬の種類を伝えて、相談から始めてみましょう。